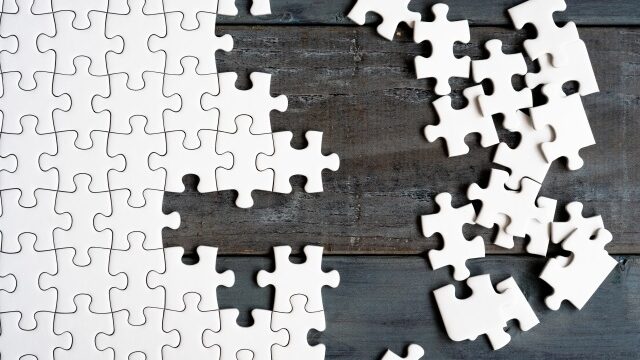毎年、初詣に多くの人で賑わう神社仏閣。
大みそかの深夜から出かけるという人もいると思いますが、本来はいつ、どこへ詣でればいいのか?喪中の時は?服装は?お賽銭やおみくじは?
改めて聞かれると、知ってるようで知らないこと、多いのではないでしょうか。
今回は、知っているようで意外と知らない初詣での作法をまとめて紹介していきます!
初詣には神社とお寺、行くならどっち?
古来の日本では、八百万(やおよろず)の神々は、人々を救うために現れた仏の仮の姿であるとして受け入れ、神道と仏教の神(仏)は同一であるとされてきました。
そして8世紀ごろには、急速に神社と寺が融合していったという経緯があります。
これを神仏習合(しんぶつしゅうごう)と言うのですが、これがベースになり、寺社を選ばず参拝するという日本独自の習慣が生まれました。
初詣とは、本来は地域の守り神様やご先祖様が眠る菩提寺への新年最初のあいさつのこと。
ですから新年を迎えたら、神社へ詣でても、お寺へ詣でても、どちららでも構わないのです。
また、初詣の回数や参拝先の組み合わせにルールはないので、神社と寺両方に初詣してもOKです。
神社に隣接してお寺が建てられていたり、お寺の敷地に神社があったりすることも少なくない為、初詣で両方に参るのは不自然なことではないのです。
神社の氏子でお寺の檀家というお家なら、迷わず両方に詣でてくださいね。
初詣に行くなら、まずは氏神様か菩提寺へ

初詣というと、有名な神社仏閣に行きたくなるところですが、まずは神社なら氏神様、お寺なら菩提寺(自分の家が檀家になっているお寺)へ行きましょう!
氏神様は地域の守り神様で、菩提寺ではご先祖様が日々あなたを守ってくれています。
初詣とは神(仏)様への新年最初のご挨拶です。
まずは日々自分を守ってくださっている一番身近にいる氏神様や先祖様に感謝の気持ちを込めてご挨拶をしに行ってください。
初詣は、行っても良い回数が決まっているわけではありませんので、有名な神社仏閣にはその後行けば良いですよ。
初詣に行く日と時間帯
初詣に行く日は、特に決まりはありませんが「歳神様」いらっしゃる7日までに行くことをお勧めします。
参拝者の多い「三が日」を避け、それ以降にゆっくりお参りするのも良いですね。
どうしても7日(松の内)までに行けないという人は、節分(旧正月)までには詣でるようにしてください。
初詣に行く時間帯にも、特に決まりはありません。
どの時間帯に行っても良いのですが、大みそかの夜は歳神様がいらっしゃるのを家で待って、元旦の朝に神様と共にお屠蘇とお雑煮をいただいた後、初詣に出向くというのが昔からの習わしです。
近年では、大みそかの深夜から年明けにかけての参拝は、二年参りといってより功徳が積めると言われています。
初詣での服装と境内でのマナー

初詣に行く時、スーツや着物を着なければならないということはありません。
ですが、カジュアルすぎる服装は避けたほうが良いですね。
神様や仏様にご挨拶しにいくのですから、なるべくきちんとしとした服装を心がけてください。
また、神様、仏様にご挨拶する時は、帽子やサングラスは外すのがマナーですよ。
境内では、他の参拝客の迷惑になるような行為(喧嘩、走り回る、大声を出すなど)や、不吉な話は控えてください。
当たり前の事ですが、ゴミのポイ捨ても禁止です。
常に神様、仏様に見られていると意識して、恥ずかしくない行動をしてくださいね。
初詣でお祓いは受けるべき?
参拝方法には、拝殿の外からお参りする「社頭参拝」と、拝殿に上がってお祓いを受ける「昇殿参拝」があります。
お祓いを受けないとご利益がないということはありませんので、どちらを選ぶかは自分の気持ち次第です。
参拝で大切なのは、真心のこもった感謝と祈りを捧げること。
厄年の人や、前年に不運にあってしまった人、社頭参拝だけでは安心できないとういう人は、初穂料を収めてお祓いを受けると良いですよ。
お賽銭はいくらあげればいい?

お賽銭の額が多いほど、ご利益がもらえるということはありません。
ご縁を願って「お賽銭は5円」という人も多いと思いますが、神社のお賽銭は神様への供え物で、お寺ではお布施です。
願いを叶えてもらう代金ではありません。
神様にいつもそばにいてもらえるよう、由緒ある建築物を守り、常に清浄を保つためのお手伝いをするという気持ちで納めてください。
神様、仏様はすべての人に平等ですから、感謝の気持ちが込められていれば少額でも大丈夫ですよ。
そしてお賽銭の納め方ですが、投げ入れるのは良くありません。
「いつも有難うございます」という感謝の気持ちを込めて、そっと賽銭箱に納めて下さいね。
願いを叶えるための正しいお願いの仕方

もしあなたが神様だったとして、挨拶も感謝の言葉もなしにいきなりお願い事をされたらどう思いますか?
「よしよし力を貸してやろう」とは思いませんよね。
お願いごとをする前に、まずは神様、仏様に新しい年を迎えられたことへの感謝の気持ちを伝えてください。
願い事は本来1回にひとつです。
あれもこれもとたくさんの欲深いお願いごとや身勝手なお願いごと、人の不幸を願うのはNGですよ。
神様、仏様はあなたの願いを叶える人ではなくて、叶えるための力を貸してくれるサポーターのような存在です。
お願いごとをするときは
「〇〇できますように」
ではなく、
「〇〇できるように頑張りますのでお力添えをお願いします」
という風にお願いするようにしてください。
願いを叶えるためには、自分自身の努力が必要です。
なんの努力もしない人に、神様、仏様は力を貸してはくれないということを忘れないでください。
生理中や喪中の時、初詣に行ってはいけない?
神道で「月経不浄」という考えはありません。
「生理中は神社に行ってはいけない」というのは、仏教の「五体不浄」という考えからきたものです。
現代ではあまり気にする必要はないと言われていますが、気になる人はあら塩を10gほど持って参拝に出かけてください。
鳥居をくぐる前に、持参したあら塩を体に振りまいても良いですよ。
喪中の時は、初詣に行くのは避けたほうがいいですね。
ただし、神社が授与するお札は、毎年新しいくしなければなりません。
地域にもよりますが、神道で五十日祭、仏教では四十九日の法要以降なら、前年のお札を納めて新しいお札を受けに行ってもよいとされています。
忌中に年末年始を迎える時は、忌明け後にお札を受けに行ってください。
もし、どうしても喪中に初詣に行きたいという場合は、鳥居をくぐらず、外から神様にご挨拶をするようにしてください。
たとえ外からでも、感謝の気持ちを伝えることはできますから。
神社での参拝方法

- 軽く一礼をして鳥居をくぐる
- 参道の中央を避けて歩く
- 手水舎で手をあらい口をすすぐ
- 賽銭を入れ鈴をならす
- 二礼二拍手一礼する
軽く一礼して鳥居をくぐる
鳥居は俗界と神様のいる聖域との境目を示しています。
一礼をして鳥居をくぐったら、そこはもう神様の神域です。
参道上に複数の鳥居がある場合は、段階を踏んで神聖な場所に近づくという意味があるので、一の鳥居から順番にくぐっていきましょう。
一礼は、鳥居をくぐるその都度してください。
神社を出るときも同じです。
参道の中央を避けて歩く
参道の中央は「正中」と呼ばれる神様の通り道です。
人は正中を避けて左右どちらかの端を歩くのが参道を歩く時の作法です。
初詣での際でも基本は同じですが、混雑している場合は各神社の指示や人の流れに従ってください。
帰る時もおなじです。
もし、参道の中央を横切る場合は、軽く頭を下げて歩いてくださいね。
手水舎で手を洗い口をすすぐ

手水舎は参拝前に心身の穢れを流し清める場所です。
右手に柄杓を持って左手を清め、柄杓を左手に持ち替え右手を清めます。
次に柄杓を右手に持ち替え、左手で水を受け口をすすぎ、その後左手をもう一度清めます。
柄杓を垂直に立てて、残りの水で柄杓の柄の部分を洗い流し、元の位置にもどします。
お賽銭を入れ鈴を鳴らす
お清めがすんだら神前に進みますが、この時も参道の端を歩くようにしてください。
お賽銭は投げ入れず、腰の高さまで手を下してそっと入れます。
お賽銭箱が遠いからという理由で、乱暴に投げ入れたりしないようにしてください。
お賽銭を入れた後、鈴があれば2~3回鳴らせばOKです。
しつこく何回も鳴らしたり、必要以上に大きく紐を振り回したりはしないようにしてください。
二礼二拍手一礼をする
まず、本殿を向いて、二回深くお辞儀をします。
次に胸の高さで左手を右手より数cmほど上に出して合わせ、ゆっくり二回拍手をします。
その後両手の指先を揃えて、神様への感謝と祈願の言葉を唱えます。
祈願の前には、自分の住所と名前を神様に告げてくださいね。
神様に感謝の気持ちと祈願を伝え終わったら、手を下してゆっくりと一回深いお辞儀をします。
複数の神様が祀られている場合
神社で祀られている神様(祭神)は神社によって異なり、祀られている神様の数も神社によって様々です。
複数の祭神を祀っている神社では、その神社の中心となる主祭神様に最初に参拝してくださいね。
お寺での参拝方法

- 山門で一礼
- 手水舎で手を洗い口をすすぐ
- 常香炉があれば煙で体を清める
- お賽銭を入れる
- 手を合わせて祈願する
山門で一礼
山門は、悟りの領域である仏殿への入り口なので一礼をしてくぐります。
左右の山門に仁王像が安置されている場合は、両方の像に手を合わせててから山門をくぐってください。
神社と違い、お寺の参道はどこを通っても構いません。
手水舎で手を洗い口をすすぐ
基本的には神社での作法と同じです。
右手に柄杓を持って左手を清め、柄杓を左手に持ち替え右手を清めます。
次に柄杓を右手に持ち替え、左手で水を受け口をすすぎ、その後左手をもう一度清めます。
柄杓を垂直に立てて、残りの水で柄杓の柄の部分を洗い流し、元の位置にもどします。
お寺によっては、手水舎がない場合もありますので、その場合は山門から本堂前に進んでください。
常香炉があれば煙で体を清める

常香炉とは、仏様にお線香を供えて、その煙を浴びることで心身を清める場所です。
常香炉がある場合は、本殿に進む前に煙を浴びて心身を清めてください。
常香炉の煙は、体の悪いところに煙をつけると治るとも言われているんですよ。
お賽銭を入れる
お寺でのお賽銭はお布施です。
欲や執着を捨てるための修行のひとつなので「お布施を受け取っていただいて有難うございます」という気持ちを込めて、賽銭箱にそっと納めてください。
手を合わせて祈願する
鈴がある場合は3回鳴らします。
なければ両手を静かに合わせて祈願します。
ご利益祈願をした後には『南無阿弥陀仏』というように、ご本尊の名前の前に『南無』をつけて唱え、手を合わせたまま深くお辞儀をします。
最後に、参拝をして功徳を積ませていただいた事への感謝の気持ちをこめて一礼します。
初詣で引いたおみくじ、引き直しはアリ?

おみくじとは、神様、仏様からのアドバイス。
1回の参拝に1回引くというのが原則です。
吉が出るまで何回も引き直しても意味がありません。
もし、おみくじで凶を引いてしまったとしても、「凶は吉に通ずる」という考え方もありますので、悲観して引き直すことはせず受け止めてください。
過去の自分振り返って、今までのやり方でよかったのか?しっかりと反省するとともに「今がどん底ならあとは上がるのみ!」と、前向きにとらえると良いですよ。
引いたおみくじは神様、仏様からのアドバイスなので、吉でも凶でも持ち歩いて大丈夫です。
持ちあるくのが嫌な人は、境内の専用の結び場に結んでください。
境内の木の枝に結ぶのはNGですよ。
お札・破魔矢の返す場所と安置場所

初詣で授与されたお札・破魔矢は、1年を過ぎたら授与してもらった神社に返します。
神社のものは神社へ、お寺のものはお寺へ返してください。
持ち帰ったお札・破魔矢は、神棚があれば神棚に安置します。
神棚がない場合は、神様を見下ろさないよう家具の上など高いところに半紙を引き、東向きか南向きで安置してください。
マンションなどで上階に人が住んでいる場合は、お札や破魔矢を人が踏むことになってしまうので、安置した天井に「雲」と書いた紙を貼っておくと良いですよ。
お札へのお供え物は、小皿にもった米、塩、水です。
米は中央に、塩は向かって右、水は向かって左に置くのが基本です。
まとめ
ふだん神社やお寺に行く事がなくても、初詣には行くという人は多いと思います。
初詣での正しい作法を知って、願いが叶うように努力してくださいね。